世界には、1日に僅かな稼ぎしか得られず食事や済むところにも困る貧困層が数多くいます。
そういった世界の貧困を解消するために、先進国からは支援が行われていますが、一方的にお金や物資を送るだけでは解決しません。
なぜなら、援助に必要な資金は無尽蔵ではありませんし、食事や住居を援助で確保できたとしても、貧困に苦しむ人たちが自身の力で生きる力を得られたわけではないからです。
本当にこの問題を解決するためには、貧困に苦しむ人たちが途上国の助けを借りることなく自立できることです。
SDGsとは
そこで鍵となるのがSDGsです。
SDGsというのは、世界で2030年までに達成しようとしている持続可能な開発目標のことを言います。
これは2015年に開催された国際サミットで採択されたもので、その目標は全部で17あります。
その1番目にあるのが「貧困をなくそう」というものです。
それ以外の目標には「質の高い教育をみんなに」とか「人や国の不平等をなくそう」といったものですが、それぞれが関連している部分もあります。
SDGsは持続可能という言葉を入れている事が重要で、前述のような一時的な援助をするといったものではなく、2030年以降は問題そのものがなくなるように世界規模で取り組もうとしています。
【参考】日本ユニセフ協会の「ユニセフハウス」とは?/見学してみえることとは?
自立を促すための取り組みを行う必要がある
ただ、問題の根はとても深く簡単に解決できるものではありません。
ただの援助ではなく、自立を促すための取り組みとなればそれなりに時間と手間そして人材を投入する必要があります。
具体的にどうすれば良いのかということで、行われているものの一つが、フェアトレードです。
フェアトレード、日本語にすれば公正な取引ですが、どういうことかというと先進国の企業などが人件費の安い途上国で商品の原材料を安く仕入れたり、製造に関わらせることを是正しようというものです。
そのフェアトレードでは商品に認証ラベルをつけることで、生産・製造でフェアトレードが行われているかどうかの区別ができます。
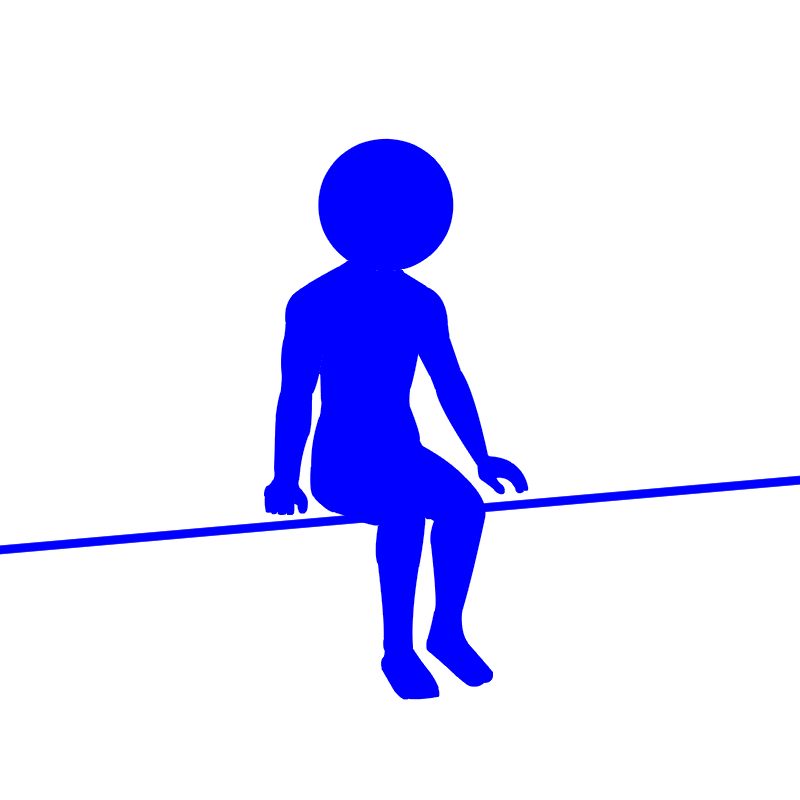
フェアトレードで仕事に見合った正当な対価を途上国の人間に支払われるようにする
なにかの仕事をするときに、先進国の人間がやれば高い報酬を支払い、途上国の人間がやると極端に少ない報酬になるのは不公正です。
そのようなことがいつまでも続けば、途上国の人間はお金に余裕がないままで生活をしなければならず、先進国の人間と同じ様になるのは難しいです。
ですから、フェアトレードを行うことで、仕事に見合った正当な対価を途上国の人間に支払われるようにすることで、誰の力も借りず自分たちで生活できるようにしていきます。
優秀な人材が多くなり途上国はより経済レベルが高まって先進国に近づける
フェアトレードが行われるようになれば、安い労働力としてこき使われている途上国の児童を救うことにも繋がります。
学校にも行かせてもらえず、毎日労働させられている児童を救えるようになれば、将来的に高等教育を受けて高い給料を得られる仕事につけるチャンスも生まれます。
そういう風にすべての児童が教育を受けられるようになれば、優秀な人材が多くなり途上国はより経済レベルが高まって先進国に近づけるでしょう。
すべての国でそういう動きになれば、世界から貧困をなくすこともできます。
材料費や人件費がそれまでの何倍、何十倍にも膨れ上がる
ただ、フェアトレードを実現するのは、そう簡単なことではありません。
公正な取引をするという仕組みは、とてもシンプルなのですが、いままでのビジネスというのは安く仕入れたり、安い人件費で働かせることで最大の利益を求めてきました。
公正な取引をするとなれば、材料費や人件費がそれまでの何倍、何十倍にも膨れ上がります。
すると、利益を得るためには商品価格を上げなければいけません。
そうなると、消費者から他のメーカーの商品よりも割高だと思われて、商品の売上が下がってしまいます。
そういったことから、メーカーはフェアトレードに消極的な姿勢になってしまいます。
もちろん、社会的な責任を果たすため、SDGsの目標達成に積極的になるメーカーもあります。
でも、全体からすればごく一部です。
フェアトレードの商品を販売するお店も少ないことが問題になっている
また、フェアトレードの商品を販売するお店も少ないことが問題になっています。
環境問題や社会問題に興味があって、そういった商品を扱うお店は少なくありません。
でもそういうお店は、ほとんどが売上があまりにない個人経営のお店ですから、経営が順調とは言えません。
フェアトレードの商品は、消費者から高いというイメージがついてしまっているため、そういうお店を利用するのは不公正な取引をなんとかしたいと思っている人だけになりやすいです。
生産・製造・販売でフェアトレードを積極的に進められない現状では、SDGsの目標達成というのは困難です。
まとめ
フェアトレードを世の中に根付かせるためには、消費者の意識を変えることが必要です。
これまで質のいい商品をお店で安く買えたのは当たり前のことではなく、影で安く働かされていた人たちがいるからだということを理解しなければいけません。
生産・製造・販売に関わる人たちが誰も不当に扱われないように、消費者が正当な対価を支払うようになれば社会は一変します。


